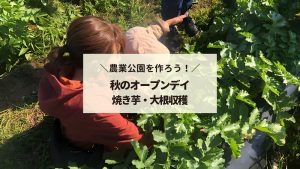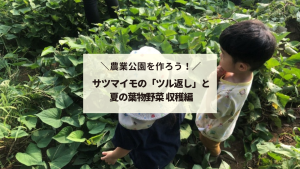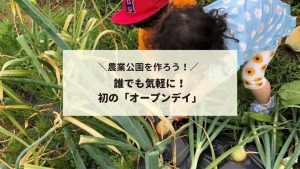多摩市連光寺で進行中の「農業公園を作ろう」プロジェクト。
うだるような暑さが続く夏。農業や家庭菜園をされている方にとって、この時期はまさに正念場ではないでしょうか。
今回は、そんな猛暑の中での野菜栽培の様子と、夏ならではのお楽しみについて紹介します。
終わりなき草刈りと、頼れる相棒の導入
「あれ?この間きれいに刈ったばかりなのに…」
畑に立つと、まるでタイムスリップしたかのような感覚に襲われます。

農業公園のある地には、多種多様な草が生えてきます。野菜たちの成長のため、大きくなる前に草を手入れしなければ、あっという間に畑を覆い尽くすほどの勢いです。
昨年は草刈りに大変苦労したため、今年は作業に新しい道具を用いることにしました。
そこで導入したのが、新しい「刈刃」です。農業公園で特に手ごわいのが、ツル性の植物である「葛(クズ)」。そのたくましい生命力で、あっという間に他の植物に絡みつき、草刈り機の刃を何度も止めてしまいます。

今年は特殊な刈刃を導入しました。 一般的な丸い刃ではなく、3つに分かれたこの刃は、蔦が絡みにくく、一振りで刈れる草の量が格段に増します。
導入してみると、作業スピードが去年の2倍近くになりました。 これからもこの頼もしい相棒と共に、草刈りを進めていきます!
新たな挑戦!「垂直仕立て栽培」
多摩市農業公園予定地では、夏にさまざまな野菜の試験栽培に取り組んできました。
上手く育ち収穫できたものもあれば、途中で生育不良が起きてしまい上手く育たないものもありました。具体的には、特に、キュウリや、トマトがなかなかうまく育っていませんでした。
そこで今年、新たな挑戦として試験的に取り組んでみたのが「垂直仕立て栽培」という農法です。 これは、野菜の枝や葉を1本の支柱に沿わせて、まっすぐ垂直に伸ばすことで植物の働きを活性化させ、元気に育つというものです。

夏野菜は横に大きく茂るため、一見すると窮屈そうに見えます。しかし、この方法を活用すると、植物ホルモンが無駄に消費されず、生育が良くなるそうです。
さて、その結果は……
一定の効果がありました!
これまで高い確率で生育不良を起こしていたキュウリは、どの苗も元気に育ち、しばらくの間、立派な実を収穫し続けることができました。ナスやミニトマトも、昨年より収穫量が増えて驚いています。


ただ、シーズン後半になると、キュウリ、ナス、ミニトマトの生育が止まってしまい、去年と同じような状態に。まだまだ課題は残ります。
とはいえ、栽培初期の生育が向上したことは大きな収穫です。
ピーマンや甘長トウガラシは継続して調子が良いので、今後もこの垂直仕立て栽培を取り入れていきたいです。

夏のご褒美!畑で味わうスイカは格別の味
夏の畑作業の厳しさばかりを話してきましたが、もちろん楽しいこともあります。
それは、とれたてのスイカを畑で食べること!
これは毎年、市民サポーターのみなさんとの夏の大きな楽しみになっています。 スイカの栽培自体は、実はそこまで難しくありません。
基本的に、植え付けたら放ったらかしでも、ある程度は育ってくれます(もちろん、摘芯や人工授粉などの手間をかければ、より立派なものができます)。
スイカは、暑くて雨があまり降らない日が続くと、より甘みが増します。日々の暑い中での作業が報われるような、自然からの贈り物です。
一番難しいのは、収穫のタイミング。 見ただけでは完熟しているかどうかの判断が難しいのです。収穫が早すぎると中が真っ白ですし、遅すぎると熟しすぎて中がドロドロになってしまいます。
だから、収穫したスイカを割る瞬間まで、毎回ドキドキです。
パカッと割れた瞬間に見える真っ赤な果肉。それが見えた時、畑には歓声が上がります。
今年の最初のスイカは…見事な赤色でした!

みんなで分け合って、その場でガブリ。 乾いた体にスイカの水分が染み渡っていき、疲れた体が不思議と軽くなります。
まさかの事件発生!?
しかし、そんなスイカにまつわる失敗談も一つ。
実は、他にもいくつかスイカが実っていたのですが、ほんの少しの隙をつかれて動物に食べられてしまいました…。

この3年間、一度も被害がなかったので、完全に油断していました。一番おいしそうな、完熟のタイミングを狙われたようで、動物の嗅覚の鋭さには感心するばかりです。
今後は、はカゴを被せるなど、しっかり対策が必要ですね。毎年、こうして成功と失敗を繰り返しながら、少しずつ学び、もっと良いものを作ることができると信じています。
鬼門の夏もあと少し。この猛暑を乗り越えれば、いよいよ秋野菜のシーズンが始まります!
(畑会 山田)